工場で働いていると、「なんでこんなに残業が多いの?」「残業って当たり前なの?」とつらく感じることもあるでしょう。残業があるのは当たり前ではないものの、さまざまな理由から常態化してしまっているケースも珍しくありません。
この記事では、工場勤務で残業が多くなりがちな原因について解説するとともに、残業を減らす方法もまとめています。ぜひ最後までお読みいただき、少しでも残業が減るように工夫してみましょう。
目 次
工場の平均的な残業時間

製造業は一般的に残業が多いイメージですが、厚生労働省の統計調査によると、製造業における一般労働者の月間所定外労働時間は15.9時間と、他業種と比べてそれほど多くありません。全体的に見ると10時間から15時間程度の残業が多い中、運輸業・郵便業の22.6時間のように製造業よりも大幅に残業が多い業種もあります。
しかし、2019年から段階的に施行されている「働き方改革」の影響もあり、製造業を含めさまざまな業種で残業時間は減ってきています。
工場勤務で残業が多くなる理由
一般的に製造業はそれほど残業が多い業種ではありませんが、中には残業時間が多い工場もあり、常態化しているケースもあります。工場勤務で残業が多くなってしまう原因には、以下のようにさまざまな理由が考えられます。
- 慢性的な人手不足
- 残業が当たり前という意識
- 業務のブラックボックス化
- 工場の生産能力不足
慢性的な人手不足
工場の残業が多くなる大きな理由として、慢性的な人手不足が挙げられます。納期までに製品を完成させなければならないため、繁忙期には特に残業が多くなる傾向があります。
繁忙期に期間工や派遣社員といった労働者を雇えない工場では、少ない人手で対応しなければならず、結果的に残業が増えてしまうでしょう。人手不足に陥るのは「業績が良くない」「人口が少なく募集をかけても集まらない」など、さまざまな理由が考えられます。
残業が当たり前という意識
作業員を含めた会社全体が「残業するのが当たり前」という意識では、残業が多くなるのも当然です。昔から残業ありきの体制、残業が会社に貢献することと同義になっているなど、古くから続いている意識を改めるのは困難でしょう。
また、残業代があるから稼げるという状況になっていると、残業を減らすための工夫をすることもないので、いつまでも残業がなくなりません。残業の多い職場風土に疑問を抱いている従業員がいなければ、改善案が持ち上がることもないでしょう。
業務のブラックボックス化
特定の業務を行える人が一人しかいないと、それぞれが担う業務に偏りが起き、結果的にチーム全体の作業が遅れて残業につながるケースがあります。業務を担当している人が急に休むときや退職する場合に、代わりに対応できる人がいないと、業務遂行に時間がかかり進捗に影響を与えることもあるでしょう。
担当者から業務の詳細が引き継がれず、担当者が変わるたびに手探りで業務を進めているような状況だといつまでたっても効率的に業務が行えません。
工場の生産能力不足
そもそも工場自体の生産能力が低いため、製造が終らず残業につながってしまうケースもよくあります。工場の機械や設備が古く製造に時間がかかる、故障やメンテナンスで稼働できない時間があるといった場合には、スケジュール通りに進まないこともあるでしょう。
工場の規模に対して受注している量が多く、生産能力に見合っていないケースも見受けられます。
残業を減らすためにできること

工場の業務で残業が発生してしまう原因には、さまざまな理由が考えられますが、工夫によって残業を減らすことが可能です。残業が多くてキツイという場合には、以下のようなアクションを試してみましょう。
- 仕事の効率化を図る
- ノー残業デーを作る
- はっきり断る
- 異動を申し出る
- 残業が少ない工場に転職する
仕事の効率化を図る
業務を見える化し、従業員それぞれの負担を分散させて、効率的に業務が行えるようにすることが残業の軽減に有効です。チーム内の誰もが作業や手順を再現できるよう仕組み化し、新しい人が入ってもスムーズに作業が行えるようマニュアル化すると良いでしょう。
一目で場所が分かるようにツールを整理する、作業スペースにある不要なものを片付けるなど、ものを探す時間の短縮や作業に集中できる環境作りが効率的な作業を可能にします。
ノー残業デーを作る
会社の制度としてノー残業デーを導入するのは、他の従業員の賛同を得たり上司に働きかけたりしなければならないので大変です。そのため、残業を減らすために、まず「自分だけのノー残業デー」を決めるところから始めてみましょう。
「今週火曜だけは絶対に残業しない」というように残業しない日を決め、徐々にチーム内に広げていくのも効果的です。従業員の中には残業したい人もいるので、完全になくすのは難しいですが、少しずつ残業を減らすことにつながるでしょう。
はっきり断る
残業を減らすためには、残業できない日ははっきりと断ることも大切です。職場によっては残業を断ると査定に響くような場合もありますが、「断らない人」と認定されて残業を押し付けられないよう、ときには勇気をもって断りましょう。
以下のような場合は、やむを得ないケースとして残業を拒否できるので確認しておいてください。
- 妊娠中又は出産から1年未満
- 養育や介護の必要がある
- 体調不良
上記に該当しなくても、36協定を結んでいない場合の時間外労働や、就業規則に反しているような場合、会社は残業を命じることができないのでしっかり断りましょう。
異動を申し出る
どうしても残業がツライという場合は、異動を申し出るのもよいでしょう。必ず異動できるわけではありませんが、残業時間を減らす方向に話が進む可能性はあります。
もちろん希望の部署に移動できるとも限りませんが、自分の意思を上司に知っておいてもらうことは大切です。ただし、会社が残業をさせたいと思っている場合、残業を断る、残業を理由に異動を願い出るといった社員は煙たがられる可能性もあるので、慎重に行動する必要があるでしょう。
残業が少ない工場に転職する
残業がない、または少ない工場に転職するのも一つの手段です。以下のように、なるべく残業がない職場を選ぶとよいでしょう。
- 交替勤務
- 徹底したマニュアル化
- 大企業の工場
2交替、3交替制の工場だと、シフトによって働く時間が決められているため、残業になることは少なくなります。マニュアル化が徹底されていて誰でもすぐに働けるような職場は、効率的に業務を進められる可能性が高いため、残業も少ないでしょう。
企業の規模によっても残業の多さに偏りがあり、多くの人が働いている大企業の方が、社会的なイメージを大切にしている影響もあり、小規模工場にくらべて残業が少ない傾向にあります。
残業を減らした方が良い理由

工場勤務では、繁忙期や納期の関係で残業が増えることがあります。しかし、長時間労働を続けてしまうと、心身の疲労がたまり、作業効率の低下やミスの増加など、さまざまな悪影響が生じます。ここでは、工場で働く人が残業を減らした方が良い主な理由に突いて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
健康への悪影響を防ぐ
工場勤務のように体を使う仕事では、長時間の労働が肉体的・精神的な負担を大きくします。特に立ち仕事や重量物の取り扱いが多い現場では、慢性的な疲労や腰痛、肩こりなどを抱える人も少なくありません。また、夜遅くまで残業を続けることで睡眠時間が減り、免疫力の低下や集中力の欠如を引き起こす可能性もあります。
さらに、過度な残業はストレスの原因にもなり、メンタル面の不調につながることもあります。厚生労働省の過労死白書によると、長時間労働が続くとうつ病や自殺リスクが高まる傾向があると報告されています。健康を維持するためにも、適切な労働時間を守ることが重要です。
仕事のミスや事故を防ぐ
残業によって疲労が蓄積すると、集中力や判断力が鈍り、作業ミスや事故のリスクが高まります。工場では重機や機械を扱う場面が多いため、一瞬の不注意が重大なケガや設備の損傷につながることもあります。
「疲れているけれど早く終わらせたい」と焦るほど、確認不足や手順ミスが起こりやすくなるのが現実です。効率的に働くためには、残業を減らし、集中できる時間内で確実に作業を終えることが理想です。結果的に、残業を減らすことは生産性を下げるどころか、品質の維持と安全の確保につながります。
プライベートの時間を確保するため
長時間残業が続くと、帰宅後に自分の時間を確保できず、家族との時間や趣味、休息の時間が削られてしまいます。一時的に残業で収入が増えても、心身のリフレッシュができない状態では、長期的なパフォーマンスの低下を招きます。
プライベートの時間を持つことでストレスを発散でき、翌日の仕事にも前向きに取り組めるようになるでしょう。また、家庭を持つ人にとっては家族との時間を確保することが精神的な支えにもなり、結果として仕事へのモチベーションアップにもつながります。
生産性とモチベーションを高めるため
「長く働いて成果を出す」という考え方は、すでに時代遅れになりつつあります。残業を前提とした働き方は、かえって社員の集中力ややる気を奪い、生産性の低下を招く傾向があります。
近年では、残業時間を減らすために業務の見える化・自動化・シフト最適化などの取り組みを行う工場が多いです。短時間で成果を出せる体制が整えば、従業員の満足度も上がり、離職率の低下にもつながるでしょう。
サービス残業の場合は対処が必要
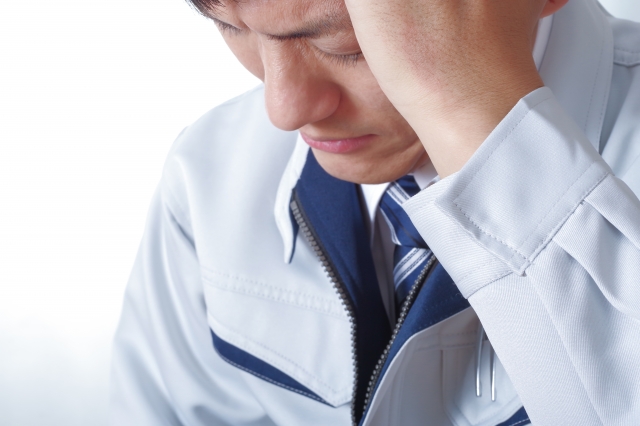
残業は、心身への負担が大きいものの、給与アップにつながるため率先して行う人がいるのも事実です。ただし、部分的に残業代が支払われない、残業代の代わりに休みを与えるなど、サービス残業が行われている場合には対処する必要があるでしょう。
また、役職がついていることを理由に残業代が支払われないのも違法の可能性があるので注意してください。残業代を支払わなくてもよいとされる「管理監督者」は、役職だけでなく、以下のような点で総合的に判断するものです。
- 経営者と同様の権限を持っているか
- 自分の裁量で労働時間を決められるか
- その地位に見合った待遇を受けているか など
このほか、さまざまな理由でサービス残業を行っている場合は、労働基準監督署に相談するといった対処が必要になるでしょう。
工場勤務の残業に関するよくある質問
工場勤務の残業に関するよくある質問に回答します。
Q. 残業代は必ず支払われるのでしょうか?
原則として、残業をした場合は必ず残業代(割増賃金)を支払う義務があります。日本の労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた分には、通常賃金の1.25倍以上の残業代を支払うよう定められています。しかし、36(サブロク)協定が締結されていない場合、会社は従業員に残業を命じることができません。また、「みなし残業」や「固定残業代制度」を採用している企業では、残業代の一部が給与に含まれている場合もあるため、雇用契約書の内容を確認することが大切です。
Q. 工場で残業を断っても大丈夫ですか?
基本的には、会社が36協定の範囲内で命じた残業を正当な理由なく拒否することはできません。しかし、以下のようなケースでは残業を断ることが可能です。
- 妊娠中または出産後1年以内
- 家族の介護や育児を行っている
- 医師の診断などで健康上の理由がある
また、そもそも36協定が結ばれていない、または就業規則で定められていない場合は、会社側に残業を強制する権限がないため、拒否できます。頻繁に長時間残業を強いられるような職場は、労働環境の改善が必要といえるでしょう。
Q. 残業が多くてつらいときはどうすればいいですか?
自分の勤務時間を客観的に把握することが大切です。「毎日2時間以上残業している」「休日出勤が多い」などの場合、体調や生活に支障が出る前に対策を取りましょう。上司に相談して改善が見られない場合は、労働基準監督署や転職エージェントに相談するのも有効です。最近では、残業が少ない工場やシフト勤務中心の職場も増えています。環境を変えることも、心身を守るためには大切です。
工場の残業が解消されない時は転職を検討
製造業は、一般的にそれほど残業が多いわけではありませんが、職場によっては常態化してしまっているケースもあります。作業を効率化する、ノー残業デーを取り入れるなど、さまざまな工夫で残業を減らすことは可能ですが、改善されない場合は転職も検討しましょう。
転職サイトやエージェントを活用し、交替勤務制、大企業の工場など、残業が少ない工場を探してみてください。




