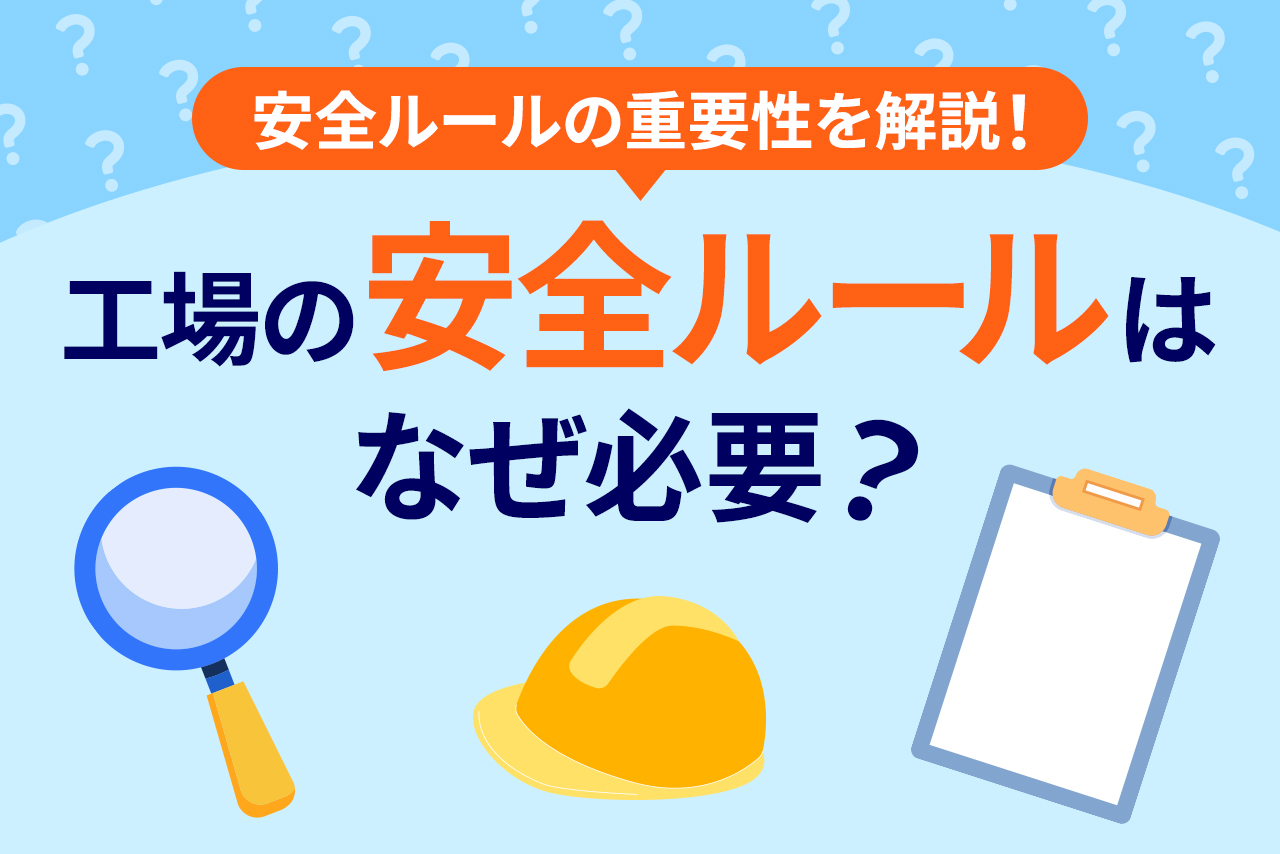工場では様々な機械が稼働し、至るところに危険が潜んでいます。機械の取り扱いを誤ったり注意を怠ったりすると、大きな事故を引き起こすこともあります。
工場で働く人全てにケガをさせないために、多くの工場では安全ルールを定めています。しかし、中には「いちいち細かいルールは守っていられない」「他の人が無視しているから自分も大丈夫だろう」と感じる方もいるでしょう。
この記事では、工場の安全ルールの重要性や、安全意識向上のための活動について解説します。この記事を読んで安全ルールの大切さを理解し、日々の仕事を見直してみましょう。
目 次
工場の安全ルールとは
安全ルールとはその名の通り、安全を確保して工場で事故や災害を起こさないために守るべきルールのことです。冒頭でも述べた通り、工場では働く人全ての人の安全を確保するために、様々な安全ルールを定めています。
例えば、
- 交差点は指差呼称してから渡る
- 作業着は腕まくりをしない
- 階段では必ず手すりを持つ
のようなものがあり、「正直毎回やるのは面倒」「やってもやらなくても変わらない」と感じる方もいるでしょう。実際に全ての人が、全ての安全ルールを守っているという工場はごく稀です。
仕事に追われていると、つい余裕がなくなってしまい安全ルールを優先できないという場面もあるでしょう。しかし、無意味に感じるような安全ルールだったとしても、とても重要な意味を持つのです。
工場の安全ルールの重要性

工場の安全ルールは、作業者の安全を守ることはもちろんですが、安全意識の高さを醸成するという役割も持っています。工場では、一瞬の油断によって大きな事故や災害に巻き込まれる危険が、至るところに潜んでいます。
安全ルールを無視し始めると、徐々に気の緩みが生じてきて、確実に守らなければならないルールですら鬱陶しく感じてきてしまいます。反対に、小さなルールでも日頃から意識して守っていれば、常に周囲の安全を気にするようになり、未然に事故や災害を防ぐことに繋がります。
事故や災害は自分が起こさないことはもちろんですが、一緒に働く仲間も起こさないように連携しなければなりません。自分が気付いた危険箇所や、注意しなければならないことは積極的に声を挙げて、周知することが大切です。自分の命も仲間の命も守るために、安全には妥協しないように心がけましょう。
さらに、工場で事故や災害が起きてしまうと、しばらくの間稼働を停止させなければなりません。バックアップできない重要な工程だった場合、自社だけでなく関係各所にも多大な影響を及ぼす可能性があり、その損害は計り知れません。
工場を正常に稼働させ、生産を確保するためにもルールを守って安全に作業することが大切です。
工場で起きやすい事故と発生原因

ここでは工場で起きやすい事故と発生原因をいくつかご紹介します。
工場で起きやすい事故とは
工場で起きやすい事故は工場の設備や取扱う製品によって異なります。一例になりますが、起きやすい事故は以下の通りです。
- 巻き込まれ事故
- 重量物との接触事故
- 車両との接触事故
- 高所からの転落事故
- 感電事故
- 高熱物との接触事故
- 歩行災害
いずれも命に関わる重大事故になりかねません。企業としては絶対に避けたい事故です。どうしてこのような事故が起きてしまうのでしょうか。発生原因を解説します。
事故の発生原因
事故の発生原因は、様々な理由が考えられます。具体例をいくつか紹介します。
- 5s(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)が徹底されていない
- 決められた手順を守っていなかった
- 点検に不備があり、機械が想定外の故障を起こした
- 通路や足元などの見通しが悪かった
- 安全に対する意識が低く、リスクを把握できていなかった
工場の安全ルールは、災害に巻き込まれないようにするだけでなく、要因をできるだけ潰して未然に事故が起こらない状態にするためにも重要なのです。
安全意識を向上するために取り組むべきこと

安全の追求に終わりはありません。以下のことを実施して、安全ルールを遵守できる職場風土を作りましょう。
- ヒヤリハット提案をする
- KYTを実施する
- 過去災害の振り返りをする
ヒヤリハット提案をする
ヒヤリハット提案とは、工場に潜む危険箇所を見つけ、それを周囲に展開する提案活動です。これは「ハインリッヒの法則」※に基づき、将来起こり得る危険をあらかじめ潰しておくことで重大災害の発生リスクを低減させるというものです。
※ハインリッヒの法則:労働災害における1つの経験則。1件の重大災害の裏には、29件の軽微な事故があり、その背景には300件の異常が潜んでいるとするもの。
- どのような箇所に
- どのような危険が潜んでいて
- どんな災害が想定されるか
- どのようにして回避するか
上記のような項目を整理して提案し、他の人が同じ危険にさらされないように周知しましょう。危険を周知するだけでなく、その危険を回避するための対策まで講じることができれば尚良いです。
KYTを実施する
KYTとは、危険予知訓練(Kiken Yochi Training)のことで、作業や職場の危険要因を特定し、解決する能力を訓練するための活動です。KYTはチーム単位で行い、様々な意見を共有することで他者の意見を取り入れ、視野の広さを養うという非常に有益な活動です。
主な手順としては、
- 作業中のイラストや写真と、作業の背景を用意する
- その情報を基にどのような危険が潜んでいるかみんなで意見を出す
- 出された意見のうち最も重要だと思うものをチームで決める
- その危険に対してどのような対策ができるか意見を出す
- 出された意見のうち最も重要な対策を決める
- それを行動目標として設定する
という流れです。
定期的に職場単位で実施し、安全意識の向上を図りましょう。
過去災害の振り返りをする
過去に実際に職場で起きた災害を振り返ることも、安全意識を向上させるために大切な活動です。新しく配属された職場では、どのような危険が潜んでいるかわからないという方がほとんどです。
実際に起きた過去の災害を振り返ることで、特に気を付けなければならない工程や、起こり得る危険を事前に把握できるため、災害の未然防止に繋がります。災害を振り返る際は、その災害が起きたときの状況や背景、それによってどのような対策が施されたのかまで詳しく振り返ると良いでしょう。
工場で定められた安全ルールの多くは、過去に起きた災害を2度と起こさないために定められています。過去の災害を振り返り、安全ルールの大切さを改めて実感しましょう。
工場の安全ルールを徹底させるための仕組みづくり

工場で定めた安全ルールを形だけのものにせず、現場全体で徹底して守っていくためには、仕組みづくりが欠かせません。単に「守るように指導する」だけでは、時間の経過とともに形骸化してしまうため、日常的に意識を高める仕掛けが必要です。ここでは、効果的な仕組みづくりの方法を紹介します。
- 朝礼やミーティングで安全共有を行う
- ポスターや掲示物で安全を「見える化」する
- 現場リーダーによる巡回・声かけ活動を強化する
- 安全教育や訓練を定期的に実施する
- 安全提案制度を設けて従業員の意見を反映する
- デジタルツールを活用して安全管理を効率化する
- 安全ルールをチームの「共通目標」として共有する
朝礼やミーティングで安全共有を行う
毎日の朝礼や定期的なミーティングで、安全に関する情報共有を行うことは重要です。例えば「昨日のヒヤリハット報告」「今週の重点安全目標」「過去の災害事例」などを共有することで、日々の作業前に安全意識を高めることができます。
また、上司やリーダーが自ら安全メッセージを発信することで、現場全体に「安全第一」という文化を根付かせることが可能です。短時間でも良いので、毎日継続的に行うことがポイントです。
ポスターや掲示物で安全を「見える化」する
安全意識を維持するためには、視覚的な情報の活用も効果的です。工場内に「安全スローガン」や「災害ゼロ日数」「ヒヤリハット報告数」などを掲示して、誰でも確認できるようにしておくと、自然と安全への関心が高まります。
また、危険エリアや作業手順を図解したポスターを設置すれば、新人や外国人労働者にも分かりやすく安全を伝えることができます。
こうした「見える化」は、注意喚起と同時に安全文化の醸成にも役立ちます。
現場リーダーによる巡回・声かけ活動を強化する
安全ルールを守る雰囲気を作るには、現場リーダーや管理職の行動が重要です。安全パトロールや巡回を定期的に実施し、危険な行動や設備不備をその場で指摘・改善する仕組みを作りましょう。
また、注意を与えるだけでなく「良い行動を褒める」ことも大切です。安全を意識して行動している従業員を積極的に評価することで、「守ることが当たり前」という風土が根付きます。
安全教育や訓練を定期的に実施する
どんなに優れたルールを作っても、従業員一人ひとりがその意味を理解していなければ効果はありません。定期的に安全教育や危険予知訓練(KYT)を実施し、ルールを「理解して守る」習慣を育てることが大切です。
新入社員研修だけでなく、ベテラン社員にも最新の安全情報を共有し、全員が同じ基準で行動できるようにすることで、工場全体の安全レベルを底上げできます。
安全提案制度を設けて従業員の意見を反映する
現場の最前線で作業を行う従業員が、最も危険や不便に気づきやすい立場にあります。そのため、「安全提案制度」や「ヒヤリハット報告制度」を設け、従業員が自発的に意見を出せる仕組みを作ることが効果的です。提案が採用された場合には、社内で共有したり、表彰するなどの仕組みを取り入れると、参加意欲が高まり安全意識の定着につながります。
デジタルツールを活用して安全管理を効率化する
近年では、タブレットやクラウドシステムを活用して安全管理を効率化する企業も増えています。点検チェックリストやヒヤリハット報告をデジタル化することで、リアルタイムに情報共有でき、記録の抜け漏れも防げます。また、AIによる映像分析やセンサーを用いた危険検知システムの導入も進んでおり、テクノロジーを活用することで人的ミスの減らすことも可能です。
安全ルールをチームの「共通目標」として共有する
安全は個人の責任だけではなく、チーム全体で守るものです。部署単位で「無災害日数」「改善提案数」などの目標を共有し、達成した際にはチーム全体で評価・表彰する仕組みを作りましょう。安全を「競う」のではなく「共に目指す」目標として扱うことで、職場全体の一体感が生まれ、安全行動の定着につながります。
工場の安全ルールを守れないときの対策

仕事に追われているときは、つい無意識に安全ルールを無視して作業に没頭してしまうこともあるでしょう。以下のことを実施して、安全ルールの遵守に努めましょう。
- 安全は何よりも優先すべきという意識を持つ
- ルールを遵守する人を評価する風土を作る
- 定期的にルールを見直す
安全は何よりも優先すべきという意識を持つ
安全というものは、作業や仕事の前提であり何よりも優先すべきものです。「安全第一」という標語をよく目にしたことがあるかと思いますが、これを本当に理解して意識できている人は意外と多くありません。
仕事に没頭していると、生産量や稼働率に目を向けがちになり、安全が二の次になってしまうこともあるでしょう。しかし、事故や災害を起こしてしまえば、それこそ生産量や稼働率を低下させることになってしまいます。
安全が確保できているからこそ、品質の良い製品を効率よく生産できるという考え方を持ち、安全を何よりも優先することを意識してください。
安全ルールを遵守する人を評価する風土を作る
工場の評価基準では、スキルや資格、業務における成果などに重点が置かれていることが多いです。そのため、安全ルールを守っていても評価に繋がらないということもあります。
それならば多少安全ルールを無視してでも、仕事を早くこなして人よりも稼働率を高くしたいと思うのも無理はありません。そうならないためにも、安全ルールを遵守する人を評価する風土や仕組み作りが大切です。
安全意識の高さが評価の対象になれば、多くの人は今よりもさらに安全を重視するようになるでしょう。今の職場に、安全ルールを守る人を評価する基準や制度がないのであれば、一度上司に提案してみるのも良いでしょう。
定期的にルールを見直す
安全ルールの中には、現状の職場環境には適さないルールもあるでしょう。昔の設備や環境では必要だったとしても、設備が新しくなったり職場環境が変わったりすれば必要ないルールもでてきます。
必要ないルールを守ろうとしても、その目的や重要性が理解できず無意識にルールを守れなくなってしまうこともあるでしょう。定期的に必要のないルールは削除する、今の環境に合わないものはアップデートするといったように、見直してみるとよいでしょう。
工場の安全ルールに関するよくある質問
工場の安全ルールに関するよくある質問に回答します。
Q1. なぜ工場では細かい安全ルールまで守る必要があるのですか?
工場は重機や高温設備、化学薬品など、常に危険と隣り合わせの環境です。「小さなルール」に見える行動でも、重大事故の防止につながる大切な意味があります。小さなルールを徹底してこそ、安全文化が根付き、大きな事故を未然に防ぐことができます。
Q2. 工場の安全ルールは誰が決めているのですか?
工場の安全ルールは、基本的に労働安全衛生法や企業の安全方針に基づいて定められています。法律で義務づけられている項目に加えて、各工場の設備・環境・作業内容に応じた独自ルールが設定されています。また、現場従業員の提案やヒヤリハット報告から新たなルールが追加されることもあります。
Q3. 新人や外国人労働者にも安全ルールを徹底させるにはどうすればよいですか?
新人や外国人労働者に対しては、「わかりやすく伝える工夫」が大切です。具体的には、実際の作業現場を使った実演教育、写真やイラストを使ったマニュアル、ピクトグラム表示などが有効です。また、外国人には母国語で説明できる教材や動画を用意し、文化の違いにも配慮した安全指導を行うようにしましょう。
Q4. 工場の安全ルールはどのくらいの頻度で見直すべきですか?
一般的には、年1回以上の定期見直しが推奨されています。しかし、新しい設備の導入や作業工程の変更があった場合は、その都度安全ルールを再点検する必要があります。現場環境の変化に応じてルールを更新し続けることが、事故を防ぐポイントです。現場の従業員の声を反映し、形骸化しないルール運用を心がけましょう。
工場の安全ルールは作業者と企業を守るためにある
企業にとって品質や生産性を上げることは大事なことですが、それ以上に大事なことは工場で働く全ての人の安全を守ることです。
なぜなら、安全な環境を確保できなれば事故が起きたり、重大クレームに繋がったりして製造どころではなくなるからです。企業の存続に関わる問題にもなりかねません。これから工場で就職する予定がある方も、すでに工場で働いている方も、安全ルールの重要性や目的を理解して、安全第一で仕事に励みましょう。