近年、働き方の選択肢が増え、ダブルワークを始める人も増えています。仕事を掛け持ちすれば収入も増加させられますが、そのぶん仕事の管理や社会保険の手続きなどが負担になることも少なくありません。
そこで今回は、ダブルワークをするうえで注意したいポイントを解説していきます。社会保険や確定申告の基礎知識もまとめているので、あわせてチェックしておきましょう。
ダブルワークってどんな働き方?

ダブルワークは、2つの仕事を掛け持つ働き方を指します。ここでは、副業または兼業との違いと、ダブルワークができない人について解説します。
副業・兼業との違い
ダブルワークが2つの本業を掛け持つのに対し、副業は、メインの仕事の収入を補うための小規模な仕事を指すケースが一般的です。また、兼業は、本業を2つ以上持つという点でダブルワークと似ていますが、公務員や農業従事者などが一時的に別の仕事をするようなケースでも使われます。
これらが主な違いにはなるものの、そこに明確な定義はないので「本業が2つ=ダブルワーク」という認識でよいでしょう。
ダブルワークができない人もいる
ダブルワークは、誰でも自由にできるわけではありません。公務員は副業や兼業が原則禁止されています。民間企業に勤める人は、就業規則で副業やダブルワークが禁止されていれば、それに従わなければなりません。
ダブルワークが許可されていても、競合他社での勤務や、会社の信用を損なうような活動は、処罰の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
雇用されている場合のダブルワークでは条件や制限が生じるので、やりたいからといって、すぐにできるとは限りません。自分の立場や所属する組織のルール、法的義務をしっかり確認し、正しく手続きを踏むことが大切です。
ダブルワークで注意したい5つのポイント

ダブルワークは二つの仕事を掛け持つため、体力的な負担が大きくなったり、保険・税金の手続きが煩雑になったりします。ここでは、ダブルワークをするうえで注意したい点を5つ解説していきます。
就業規則に違反していないか
あなたがフリーランスや自営業でない場合、ダブルワークを始める際には、まずは勤務先の就業規則を確認する必要があります。副業や兼業を全面的に禁止している企業もあり、違反すれば社内での立場が悪くなりかねません。
近年、副業を認める企業も増えてはいますが、「事前申請が必要」「副業の内容を報告する」といった条件付きのケースも多く、黙って始めるのはリスクが高いです。働き方の自由が認められているとはいえ、雇用される立場であることを忘れないようにしましょう。
体調管理を徹底する
ダブルワークは、時間と体力的な負担が大きくなりがちです。とくに1日に2つの仕事を掛け持つような場合は、労働時間が長くなり、慢性的な睡眠不足や疲労に陥ることもあります。これにより体調を崩してしまえば、収入どころかすべてを失いかねません。
忙しいからこそ無理をせず、自分の生活リズムや体力と向き合いながら働き方を調整する必要があります。しっかりと休息を取り、栄養バランスの取れた食事、運動を意識するなど、健康を守る努力は必須です。
保険や税金などの管理が必要になる
ダブルワークをすると、社会保険や税金の手続きが複雑になることがあります。複数の会社で雇用される場合、どちらの職場でも一定の勤務条件を満たせば社会保険への加入が必要です。
また、以下のような人は、確定申告の必要性も生じます。
- 2つ以上の会社に勤務し、1か所で年末調整を行っている
- 2か所以上で年末調整をした
- そもそも年末調整がない
- 20万円以上の副収入がある
税金を適切に処理しないと追徴課税が発生するリスクがあるので、ダブルワークを始める前に、税務署や社会保険事務所など、専門家に確認しておくと安心です。
複数の会社に雇用される場合は報告を
ダブルワークで複数の会社に雇用される場合、雇用保険や社会保険の扱いに関して正確な情報共有が必要です。
たとえば、雇用保険は1か所で加入することになりますが、条件を満たさなければどちらでも加入できません。黙って掛け持ちをすると、労働条件の調整ミスや保険の未加入など、トラブルの元になることもあるので注意が必要です。
それぞれの仕事に負担がかからないよう注意
ダブルワークは、収入面でのメリットがある一方で、各仕事に対する責任や集中力の維持が難しい側面もあります。どちらかの仕事が負担になり、もう片方の職場でミスや遅刻、欠勤などを繰り返せば、信用を失いかねません。
また、仕事のスケジュールが重なる、急なシフト変更に対応できないといった事態も起こりがちです。そのため、それぞれの職場に対して誠実でいるためには、自分の時間とエネルギーを適切に配分する必要があります。
ダブルワークの社会保険
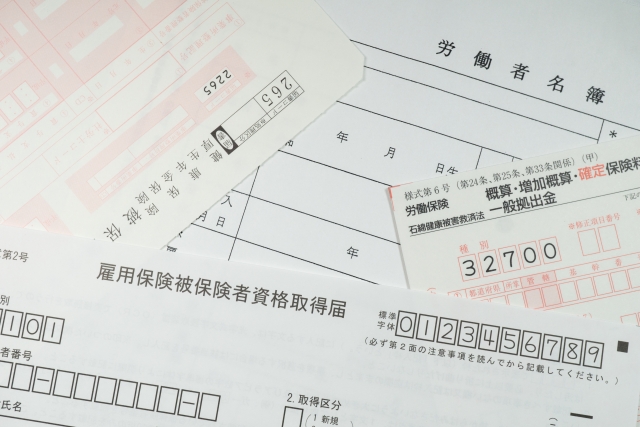
ダブルワークをする場合、社会保険の加入も単一の勤務先で働く人とは違ってきます。加入状況によっては負担が大きくなるため、条件などを把握しておきましょう。
二重加入が可能
複数の勤務先ごとに社会保険の加入条件を満たしていれば、それぞれの職場で社会保険に加入することになります。主な加入条件は以下のとおりですが、企業の規模や働き方によって異なるため、人事部などに確認しましょう。
- フルタイムまたは週の労働時間が20時間以上
- 月収88,000円以上
- 2か月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない
ただし、二重加入するためには「二以上事業所勤務届」が必要になり、被保険者自らが手続きしなければなりません。また、いずれの勤務先でも、条件を満たさなければ社会保険には加入できないので注意してください。
二重加入のメリット・デメリット
厚生年金は報酬比例なので、社会保険に二重で加入すると、将来の年金受給額が増える可能性があります。健康保険でも、傷病手当や出産手当金など、より充実した保障を受けられるのがメリットです。
一方、デメリットは、保険料の負担が増える点です。報酬が高いほど保険料が上がり、それを雇用主と労働者が折半するため、勤務先によっては嫌がられることもあるでしょう。
制度自体が複雑で、手続きもややこしいため、会社側に説明が必要だったり、理解されにくかったりするケースもあります。
保険料の計算方法
複数の勤務先でそれぞれ社会保険に加入する場合、保険料の計算はすべての収入の合計額をベースに行われます。
A社で月収12万円、B社で月収15万円だった場合、合算した27万円をもとに標準報酬月額が決まり、それに応じて健康保険・厚生年金の保険料が算出されます。その後、事業所ごとの報酬に比例して按分され、各事業所がそれぞれ保険料を負担する流れです。
地域や保険組合によって料率が異なる場合があるため、所属する健康保険組合の情報を確認しておきましょう。
【ダブルワーク】年末調整と確定申告

掛け持ちで働く人には、年末調整と確定申告も重要なポイントになります。正確に税金を納めるためにも、基本的なことを確認しておきましょう。
年末調整は1か所で
年末調整は、基本的に1か所の勤務先でしか行えません。「主たる給与所得者」として選んだ会社に限られ、その会社で扶養控除や保険料控除などの各種控除を適用する手続きを行います。
年末調整を行う勤務先には「扶養控除等申告書」を提出しますが、もし両方の会社に提出してしまった場合は、片方に取り下げてもらう必要があります。もし取り下げが間に合わなければ、自分で確定申告を行い、正しく処理しましょう。
確定申告が必要になる条件
ダブルワークで確定申告が必要になるのは、前述の例のように、2か所で確定申告を行ったケースに限りません。最も一般的なのは、年末調整を行っていない給与、または副収入が年間20万円を超えた場合です。
また、2か所以上から給与を受けていてどちらの勤務先でも年末調整をしていない、医療費控除・住宅ローン控除を受けたいといった場合も、確定申告が必要です。
条件に当てはまらなければ確定申告は不要ですが、源泉徴収で多く引かれている場合は還付があるので、できるだけ申告することをおすすめします。
ダブルワークは注意点を事前に確認
ダブルワークでは、労働時間が増えることによる肉体的な負担と、社会保険などの加入に関する手続きなどの負担が大きくなる可能性があります。働き方や税金、確定申告について事前に注意点を確認しておきましょう。
これらについてわからないことがあるときは、必要に応じて勤務先の人事部や各機関に問い合わせるのがおすすめです。




