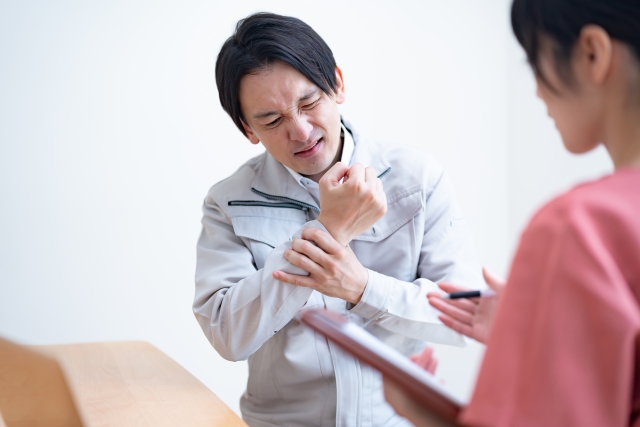労災保険は業務中や通勤中の事故から労働者を守る仕組みですが、適切に対応できなければ企業は大きなリスクを抱えることになります。とくに派遣社員の場合、派遣元と派遣先の役割分担を正しく理解し、迅速かつ誠実に対応することが重要です。
今回は、派遣先企業向けに、労災の基本と派遣先企業がするべきことについて解説していきます。対応の注意点もまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
労災とは
まずは、労災の概要を確認しておきましょう。
労災保険制度と対象
労災保険制度は、労働者が業務中や通勤中に負傷したり病気になったり、あるいは死亡したりした場合に、その被害を補償するための公的な仕組みです。正式名称は「労働者災害補償保険」で、事業主が全額負担して保険料を納めます。
対象となるのは正社員だけでなく、パートやアルバイトのほか、派遣労働者も含まれます。労働者を守ることを目的としているため加入は任意ではなく、原則としてすべての事業に適用されるのも大きな特徴です。
一般企業や建設現場、飲食店など幅広い業種の労働者を対象にしており、労働者が安心して働ける基盤を支えています。
業務災害
労働者が、業務を遂行する過程で発生した事故や病気を「業務災害」といいます。たとえば、次のような例が挙げられます。
- 製造業での機械操作中の指の切断
- 建設現場での落下事故
- 飲食店での火傷や転倒
- 過重労働による疾患やメンタルの不調 など
業務災害と認められるには、業務に従事している時間・場所で発生したこと、かつ仕事そのものが原因であることが重要です。労災認定されれば、療養費や休業補償、障害補償などが給付されます。
近年では、過労死、自殺といった労働時間やストレスに関連する事例も業務災害として扱われるケースが増えています。
通勤災害
労働者が、住居と職場との間を適切な経路で移動する際に発生した事故や怪我は「通勤災害」とみなされます。例として挙げられるのは、次のようなケースです。
- 通勤中の交通事故
- 駅やバス停での転倒
- 自転車の事故 など
ここで重要なのは、合理的な経路と通勤方法であることです。通常の通勤ルートを外れて私的な寄り道をした場合、その区間での事故は通勤災害に該当しない可能性があります。
ただし、工事による迂回や子どもの送迎など、社会通念上合理的と認められる行為であれば対象となるケースもあります。
労災保険給付の種類
労災が認められると、下表のような給付が受けられます。
| 療養補償給付 | 窓口での自己負担が不要になるほか、医療費は原則すべて労災保険から支払われる |
|---|---|
| 休業補償給付 | 負傷や病気のため働けず、賃金を受けられない期間に支給される |
| 障害補償給付 | 治療が終わっても後遺症が残った場合に、年金または一時金として支給される |
| 遺族補償給付 | 労災が原因で労働者が亡くなった場合に遺族に支給される |
| 傷病等年金 | 療養開始から1年6ヶ月経過しても治らず、労働能力が失われている場合に支給される |
| 介護補償給付 | 障害や傷病によって日常生活で介護が必要な労働者に支給される |
派遣社員の労災は派遣元・派遣先どちらが対応する?
派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、派遣元企業が労災保険に関する法的な責任を負います。ただし、書類の作成にあたっては、事故当時の正確な状況を把握する必要があるので、派遣先に協力を求めることもあります。
派遣元は派遣先から事故の状況を速やかに報告してもらい、必要な証拠書類を整えて労働基準監督署へ提出しなければなりません。派遣会社には、労災事故後の職場復帰支援や再発防止策を派遣先とともに講じる責任もあります。
派遣社員の労災で派遣先企業がすること
派遣社員の労災に対しては基本的に派遣会社が対応しますが、派遣先企業でもすべきことがあります。以下、派遣先企業の対応について確認しておきましょう。
派遣会社・派遣社員への説明
労災事故が発生した際は、適切に対処したあと、派遣会社に連絡するよう派遣社員に伝えましょう。また、派遣会社や派遣社員本人に聞かれた場合には、事故の原因などについて説明する必要があります。
労災保険の申請は派遣元が主体となりますが、派遣先が事故の詳細を正確に伝えなければ、労基署の調査や労災認定に支障が生じます。そのため、派遣先は主に以下の点について説明できるよう、情報を整理しておきましょう。
- 業務のどの段階で事故が起きたのか
- 作業指示の状況
- 安全管理体制に問題がなかったか など
さらに、事故後の勤務扱いや休業についてを派遣会社と共有し、派遣社員の不安を軽減することも大切です。
医療機関への提出書類の作成
派遣社員が労災で負傷した場合は、医療機関に提出する書類に派遣先の情報を記入しなければなりません。具体的には、派遣会社が作成する「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」の、派遣先証明欄を記入し、事故の状況、負傷した日時などを書き込みます。
これは、派遣社員が治療を受ける際に必要な書類で、事故の発生状況や業務との関連性を証明する部分を派遣先が記入しなければなりません。提出書類に不備や遅延があると労災認定が長引き、治療費の自己負担が発生するなど労働者に不利益が及ぶ恐れがあります。
そのため派遣先は、事故発生直後から状況を詳細に記録し、医療機関や派遣元に迅速かつ正確に情報を提供する体制を整えることが重要です。
労働者死傷病報告の作成
派遣社員が、労災事故により死亡または4日以上の休業が必要な負傷・疾病を負った場合、派遣先は「労働者死傷病報告」を作成し、労働基準監督署と派遣会社へ提出しなければなりません。これは労働安全衛生法に基づく法的義務であり、派遣社員であっても自社の事業場で発生した労災として報告する必要があります。
報告内容には、主に以下の項目が含まれます。
- 事故発生の日時・場所・原因
- 負傷の程度
- 再発防止策 など
派遣元が労災保険の給付申請を行うのに対し、派遣先は安全管理上の責任者として、事故を正しく把握・記録し、行政に報告する立場です。この報告を怠ると、行政指導や罰則の対象になるだけでなく、労働安全衛生管理体制の不備として信頼を失うリスクもあります。
【労災】派遣先企業の注意点
労災が発生した際、派遣先企業は、派遣労働者に不利益がないよう適切に対応しなければなりません。たとえ意図的でなくても、違反行為があれば企業の信頼が失われる恐れがあるため、注意点を押さえておきましょう。
申請期限に注意
労災が発生した場合、派遣先企業は事故状況の証明や医療機関への書類提出の作成などに速やかに協力しなければなりません。労災保険の給付請求は、原則として以下のように期限が定められています。
- 療養補償給付:事故発生日から2年以内
- 休業補償給付または遺族補償給付:5年以内
申請が遅れれば労働者が給付を受けられなくなるリスクがあり、派遣社員とのトラブルや企業イメージの低下につながりかねません。期限管理を徹底することは、派遣社員の生活を守るだけでなく、企業の法令順守と信頼性確保のためにも大切です。
労災ハラスメントの発生を防止
労災が発生すると、休業や治療によって業務に影響が出る場合があります。このとき派遣先が次のような対応をすると、労災ハラスメントとして大きな問題になる可能性があります。
- 労災申請を思いとどまらせる発言
- 事故の責任を派遣社員に押し付けるような態度
- 復帰後に業務から外すなどの対応
こうした職場での言動や態度は派遣社員に過度な負担を与え、さらなるトラブルに発展しかねません。派遣先には、労災が発生した従業員に対し中立的かつ支援的な姿勢を保ち、安心して療養・復帰できる環境を整えることが求められます。
労災が発生したら派遣先は適切に対処する
派遣社員に労災が発生した場合、主な対応は派遣会社が行いますが、派遣先企業も適切に対処する必要があります。申請に時間がかかると派遣社員に不利益が生じる可能性があるため、事故の状況を正確に把握し、派遣会社がスムーズに労災申請できるように協力しましょう。
事故の責任を派遣社員のせいにする、労災隠しに協力させるといった行為はハラスメントや法律違反に該当する可能性があるため、絶対に避けてください。派遣社員が安心して治療に専念できるよう中立な立場を守ることが、自社のコンプライアンス意識や職場の信頼性を高めることにもつながります。